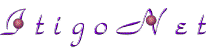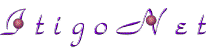| 碓氷第6橋梁 |
![]()
|
碓氷第三橋梁(めがね橋) |
![]()  横川と軽井沢を結ぶアプト式鉄道が開通したのは 明治26年(1893)でした すでに上野−高崎間は明治17年(1884)に開通し 19年から21年には 直江津−軽井沢間が開通していたので これにより東京と信越を結ぶ鉄道が完成した 横川と軽井沢を結ぶアプト式鉄道が開通したのは 明治26年(1893)でした すでに上野−高崎間は明治17年(1884)に開通し 19年から21年には 直江津−軽井沢間が開通していたので これにより東京と信越を結ぶ鉄道が完成した
 碓氷峠越えの鉄道は 群馬や長野の蚕糸業に大きな影響を与えただけでなく近代日本の工業化の推進にみ重要な役割を果たしました 碓氷峠越えの鉄道は 群馬や長野の蚕糸業に大きな影響を与えただけでなく近代日本の工業化の推進にみ重要な役割を果たしました
この碓氷線に残された橋梁の一つがこの第6橋梁です 第6橋梁は アーチ径間が11.0メートル 高さ17.4メートル 頂部長さ51.9メートルで 隅角部を切石で補強し高い橋台と片蓋柱と長い側壁を持っています
長さやレンガの使用量では第三橋梁に次ぐ規模のものです と説明されています
|
![]()  碓氷第三橋梁(めがね橋)は 碓氷線と呼ばれた横川−軽井沢間は 碓氷峠が急勾配のため 線路決定に紆余曲折し 明治26年(1893)4月開業となり 高崎−直江津間の全線が開業しました 碓氷第三橋梁(めがね橋)は 碓氷線と呼ばれた横川−軽井沢間は 碓氷峠が急勾配のため 線路決定に紆余曲折し 明治26年(1893)4月開業となり 高崎−直江津間の全線が開業しました
 横川−軽井沢間の11.2キロメートルは 千分の66.7という最急勾配のため ドイツの山岳鉄道で実用化されていたアプト式が採用され 昭和38年まで走り続けました 横川−軽井沢間の11.2キロメートルは 千分の66.7という最急勾配のため ドイツの山岳鉄道で実用化されていたアプト式が採用され 昭和38年まで走り続けました
この碓氷線には 当時の土木技術の粋を集めて 26のトンネルと18の橋梁が造られましたが なかでもこの第三橋梁は200万個以上のレンガを使用した 国内でも最大のレンガ造アーチ橋です
径間数4 長さ87.7メートル 昭和38年9月に新線の完成と同時に使用廃止となっています
|
|
| 丸山変電所 |
霧積 66.7パーミル |
![]()  アプト式鉄道電化の際に軽井沢の矢ケ崎変電所とともに建設された施設で 蓄電池室と機械室の2棟が建てられています 用途廃止後もそのまま荒れるままに放置され 旧信越本線の車窓からは窓が割れ 天井が落ちているなど 痛ましい姿を何度となく見たものです アプト式鉄道電化の際に軽井沢の矢ケ崎変電所とともに建設された施設で 蓄電池室と機械室の2棟が建てられています 用途廃止後もそのまま荒れるままに放置され 旧信越本線の車窓からは窓が割れ 天井が落ちているなど 痛ましい姿を何度となく見たものです
 信越本線廃止後に遊歩道の整備にあわせて復元工事が行われ 平成14年(2002)に完成しています 今回の旅ではトロッコに乗車しましたが トロッコは丸山駅に停車せずに通過しました ホームの改札にロープが張られていて駅自体が閉鎖されていました 信越本線廃止後に遊歩道の整備にあわせて復元工事が行われ 平成14年(2002)に完成しています 今回の旅ではトロッコに乗車しましたが トロッコは丸山駅に停車せずに通過しました ホームの改札にロープが張られていて駅自体が閉鎖されていました
旧信越本線の特急「あさま」で通過する際 丸山変電所の周辺は コスモスの畑が広がる秋の花の名所でもありました
|
![]()  国道18号線の旧道を霧積温泉に向う道路沿いに旧信越本線の線路跡が残されています この直線の区間をスラッジ 架線とのスパークの青白い光の連続させながら駆け上がるEF63の重連 そして軽井沢から横川に向う上り線は 低いブロワー音を轟かせて駆け下りるEF63を眺めたものです 国道18号線の旧道を霧積温泉に向う道路沿いに旧信越本線の線路跡が残されています この直線の区間をスラッジ 架線とのスパークの青白い光の連続させながら駆け上がるEF63の重連 そして軽井沢から横川に向う上り線は 低いブロワー音を轟かせて駆け下りるEF63を眺めたものです
さかもと・やがさきの夕日は旅の旅情 レンガに溶け込むエンブレム 夕闇に光るライト 金色に輝くサイドライン
夕日に照らされた66.7パーミルの勾配票にヘットライトの光が輝く いている・・・
平成9年(1997)9月30日の廃止の日まで 何度となく通い詰めた あの日が昨日のように思い出されます
|
|
| とうげのゆ駅近くの旧信越本線下り線 |
とうげのゆ駅 |
![]()  平成9年(1997)9月30日 信越本線 横川−軽井沢間の最終運行日 写真のトンネルの左手前でビデオ撮影をしていました 廃止当日 上野行き特急「あさま」の最終便の1列車前で横川に向かい 最終便の「あさま」を横川駅で迎えました ダイア上はこの特急が最終の横川−軽井沢間の列車でしたが こののち臨時の普通電車が運行され この普通電車が上りの最終旅客電車になります 平成9年(1997)9月30日 信越本線 横川−軽井沢間の最終運行日 写真のトンネルの左手前でビデオ撮影をしていました 廃止当日 上野行き特急「あさま」の最終便の1列車前で横川に向かい 最終便の「あさま」を横川駅で迎えました ダイア上はこの特急が最終の横川−軽井沢間の列車でしたが こののち臨時の普通電車が運行され この普通電車が上りの最終旅客電車になります
その後 下り列車で軽井沢に向かい 長野行きの最終の特急「あさま」を軽井沢駅で見送りました
 碓氷峠の実際の最終便はEF63の横川への回送です 二度と戻ることのない軽井沢駅 横川−軽井沢間は 線路距離が11.2キロメートル 水平距離が約9.2キロメートル 特急「あさま」との協調運転だけでも約12万往復 その最後の出発 長い汽笛とテールランプに涙したものです 碓氷峠の実際の最終便はEF63の横川への回送です 二度と戻ることのない軽井沢駅 横川−軽井沢間は 線路距離が11.2キロメートル 水平距離が約9.2キロメートル 特急「あさま」との協調運転だけでも約12万往復 その最後の出発 長い汽笛とテールランプに涙したものです
|
![]()  碓氷峠鉄道文化むら内から碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」までの約2.6キロにトロッコ列車が運行されています 線路は平成9年に廃止された旧信越本線の下り線をそのまま使用しています 碓氷峠鉄道文化むら内から碓氷峠の森公園交流館「峠の湯」までの約2.6キロにトロッコ列車が運行されています 線路は平成9年に廃止された旧信越本線の下り線をそのまま使用しています
 右の写真は旧信越本線の下り線から峠の湯の駅に新たに敷設されたトロッコ専用線です 旧信越本線の下り線のその後は 左の写真のように草に覆われた廃墟となっています できれば 峠の湯の駅までEF63がプッシュバックする運行ができないのか あのブロワー音とともに峠を登りたいと思うのは私だけでしょうか 右の写真は旧信越本線の下り線から峠の湯の駅に新たに敷設されたトロッコ専用線です 旧信越本線の下り線のその後は 左の写真のように草に覆われた廃墟となっています できれば 峠の湯の駅までEF63がプッシュバックする運行ができないのか あのブロワー音とともに峠を登りたいと思うのは私だけでしょうか
 峠の湯は 平成25年7月31日未明の火災によって営業していません 早期に再開できるとよいのですが 今後が心配です 写真のように焼け落ちています 本当に残念でなりません 峠の湯は 平成25年7月31日未明の火災によって営業していません 早期に再開できるとよいのですが 今後が心配です 写真のように焼け落ちています 本当に残念でなりません
|
|
| 旧熊ノ平駅 |
碓氷峠鉄道文化むら |
![]()  熊ノ平駅は 碓氷峠が単線であったため 上り列車と下り列車のかれ違いと 蒸気機関車への給水・給炭の目的で設置されました 碓氷線は間線鉄道でありながら その急勾配ゆえアプト式という特殊運転方式をとらざるを得ず 動脈に出来た血栓のように隘路となってしまう宿命を負っていました このため碓氷線には 常に輸送力の増大が求められ 新技術の投入によって解決が図られ 熊ノ平駅も待避線の設置や突っ込み隧道の設置などの改良を加えられました 熊ノ平駅は 碓氷峠が単線であったため 上り列車と下り列車のかれ違いと 蒸気機関車への給水・給炭の目的で設置されました 碓氷線は間線鉄道でありながら その急勾配ゆえアプト式という特殊運転方式をとらざるを得ず 動脈に出来た血栓のように隘路となってしまう宿命を負っていました このため碓氷線には 常に輸送力の増大が求められ 新技術の投入によって解決が図られ 熊ノ平駅も待避線の設置や突っ込み隧道の設置などの改良を加えられました
 碓氷線は急勾配のため 隧道が煙突の役割を果たし 煤煙によって乗客や乗務員が大変な苦痛を強いられました この煤煙問題の解決と輸送力増大のため 明治45年 我が国の幹線鉄道として初めて電気機関車が導入されました 碓氷線は急勾配のため 隧道が煙突の役割を果たし 煤煙によって乗客や乗務員が大変な苦痛を強いられました この煤煙問題の解決と輸送力増大のため 明治45年 我が国の幹線鉄道として初めて電気機関車が導入されました
その後 昭和38年アプト式の旧碓氷線の廃止と 昭和41年の碓氷新線の複線化により 熊ノ平駅は信号場に降格となり 平成9年の碓氷線の廃線とともに使命を終えました
熊ノ駅周辺は 紅葉の名所としても知られ 文部省唱歌「紅葉」の作者の高野辰之がこの周辺の紅葉を詠ったと云われています
|
![]()  碓氷峠鉄道文化むらは 旧横川機関区の建物と敷地を利用して開園した施設です 横川機関区は 旧碓氷線が明治26年の開通から平成9年の廃線まで 蒸気機関車 アプト式電気機関車 粘着式電気機関車の基地として歴史を重ねた信越本線の重要拠点です 碓氷峠鉄道文化むらは 旧横川機関区の建物と敷地を利用して開園した施設です 横川機関区は 旧碓氷線が明治26年の開通から平成9年の廃線まで 蒸気機関車 アプト式電気機関車 粘着式電気機関車の基地として歴史を重ねた信越本線の重要拠点です
園内には30以上の展示車両があり国内各地で活躍した蒸気機関車 電気機関車 気動車等が屋外展示等されています なお 屋外展示のため風雨による経年劣化が著しいのが残念でなりません
 右の写真は 横川駅の写真です ホームは旧下り線のホーム 右側の駐車場の部分は横川機関区に向う線路があった場所です EF63型電気機関車が重連で駐機していた思い出の場所です 何度も長野と上野を往復した信越本線の横川−軽井沢間 横川駅で峠の釜飯の駅弁を買い また 駅のそばを食べた駅 重いではつきません 右の写真は 横川駅の写真です ホームは旧下り線のホーム 右側の駐車場の部分は横川機関区に向う線路があった場所です EF63型電気機関車が重連で駐機していた思い出の場所です 何度も長野と上野を往復した信越本線の横川−軽井沢間 横川駅で峠の釜飯の駅弁を買い また 駅のそばを食べた駅 重いではつきません
|
|
| 上信越自動車道 横川SA 上り線 急行「志賀号」 |
横川−軽井沢間の運行最終日 |
![]()  上信越自動車道の横川SAの上り線の店内には急行「志賀号」に使われていたディゼル電車の車体が展示されています 車内に入ることもでき また 車体の近くには 横川駅名物の駅弁 「峠の釜飯」 も販売され 車内に持ち込んで食べることもできます 昭和33年2月1日から旧国鉄信越本線横川駅で販売が開始された 「峠の釜飯」 長野県に住んでいたとき 写真のディーゼル急行には乗車したことはありませんでしたが 特急 「あさま」 や 普通電車の189系「志賀号」でなんども往復したものです 上信越自動車道の横川SAの上り線の店内には急行「志賀号」に使われていたディゼル電車の車体が展示されています 車内に入ることもでき また 車体の近くには 横川駅名物の駅弁 「峠の釜飯」 も販売され 車内に持ち込んで食べることもできます 昭和33年2月1日から旧国鉄信越本線横川駅で販売が開始された 「峠の釜飯」 長野県に住んでいたとき 写真のディーゼル急行には乗車したことはありませんでしたが 特急 「あさま」 や 普通電車の189系「志賀号」でなんども往復したものです
上信越自動車道 横川SA 上り線 急行「志賀号」上の写真または 志賀号 でご覧ください
|
![]()  写真は碓氷峠が廃線となった当日のEF63の写真です 写真は碓氷峠が廃線となった当日のEF63の写真です
66.7パーミルの急峻な峠のシェルパEF63型直流電気機関車 通過する全列車の麓側に必ず重連で連結し 登り勾配は車両を押し上げ・下り勾配は車両の全重量に耐えながら峠を下るじつに頼しい機関車でした 製造車両数25両・L特急"あさま"との協調運転だけでも約12万往復 やさしいマスクと秘めた力はもう峠のレールに見ることはできません
往時の思い出を永遠に残すために 横川駅に隣接した旧横川運転区の跡地に鉄道村があります EF63 そして日本全国で活躍した機関車 客車たち みなさんが逢いに来てくれる日をまっています
静かに時を刻んだ碓氷峠の歴史がよみがえっています。二度と戻らない瞬間が !!
廃止当日の写真と動画は上の写真または EF63型電気機関 でご覧ください
|