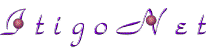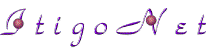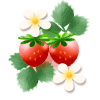|
 ■加勢川ふるさと水回廊 「中無田閘門」 ■加勢川ふるさと水回廊 「中無田閘門」
 現在の緑川は加藤清正によって形づけられ、その後、大正から昭和後期にかけて大改修、さらに平成の大改修と人々の願いを込めて、安全で河川環境豊かな川づくりが進められています。 現在の緑川は加藤清正によって形づけられ、その後、大正から昭和後期にかけて大改修、さらに平成の大改修と人々の願いを込めて、安全で河川環境豊かな川づくりが進められています。
この中無田閘門は、下流1キロにある六間堰の新設により船の航行ができなくなるために、昭和17年(1942年)、当時の最新の技術を駆使して造られ、船の大きさや洪水、潮の潮位・水圧などを考え、水位差のある緑川と加勢川を船がスムーズに航行できるよう建設さけており、ゲートは建設当時と同様木製ゲート(米松)であります。現在でも多くの人々に利用され、全国でも数少ない施設でもあります。川は生活の知恵と歴史が多く残されており、この中無田閘門は川の文化を知る大切な遺産で、先人たちの夢と願いを込めた川づくりを学び、私たちは今からも大切に活かし、守っていきたいものです。と説明されています。
■緑川下流部河川事業の変遷 「加藤清正の緑川づくり」
 天正16年(1588年)加藤清正が入領すねまでの熊本は、自然に近い河川の流れで米の生産も54万石であったが、加藤清正1代の28年間で73万石の領地に拡大した。それは開墾・干拓の努力もよるが、その背景には河川の改修は見逃すことはできない。 天正16年(1588年)加藤清正が入領すねまでの熊本は、自然に近い河川の流れで米の生産も54万石であったが、加藤清正1代の28年間で73万石の領地に拡大した。それは開墾・干拓の努力もよるが、その背景には河川の改修は見逃すことはできない。
現在の緑川の原型は当時築かれたもので、加勢川に注ぐ御船川を緑川本流に変え、加勢川の右岸に清正堤と緑川右岸に大名堤を築き、国道3号線上流に「呑吐(どんと)の堤」を設け杉島新川を堀り、洪水時の越流と宇土一帯160町余への農業用水を確保すると共に、川尻への船の水路づくりと下流の河床の上昇を防ぐ川づまりを行った。
■「昭和初期の大改修」
大正13年から昭和16年にかけて緑川・加勢川の大改修が施され、その狙いは洪水に備えた治水工事と、干拓によって広がった地区への農業用水の確保が主で、緑川の拡幅工事と共に呑吐の堤の上流に上杉堤が設けられ、加勢川が河口から9キロの地点で緑川と合流していたのを、河口から5キロで合流させながら天明地区への灌漑を豊かにし、新加勢川を川尻に直接通すと共に、船の水路確保のため中無田閘門を新しく設けたものの、時代と共に船運から車輛に変わりつつあることがこの河川工事からも伺い知れます。
■「平成の大改修」
熊本に入城した加藤清正は熊本の城下町を水害から守ると共に、薩摩藩島津氏の攻撃に備え、江津塘、本部塘と呼ばれる清正堤を加勢川の右岸のみに築き熊本城の第3の外堀と考え、約400年間もの長い間、左岸の敷島地区は堤防がなく毎年数度の洪水に見まわれていました。敷島地区を中心に加勢川流域を洪水から守る目的で、江津湖下流の大六橋から六間堰の約11キロ強の区間で、加勢川の拡幅工事と左岸の築堤、右岸の補強工事が進められると共に、洪水の原因であった六間堰の拡幅と移動堰の施工により、安心な洪水対策と共に環境復元に向けた取り組みが進められています。と説明されています。
|